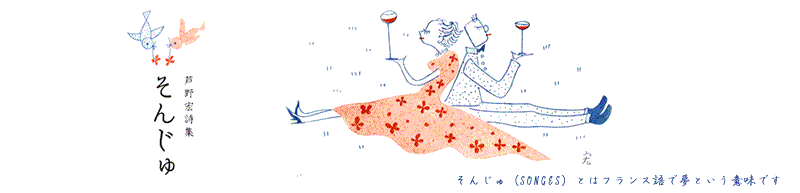幸福を売る男
芦野 宏
Ⅱ 夢のような歌ひとすじ
1、ポピュラーの世界へ
ダミアの来日-1
さて、昭和二十八年二九五三)五月三日、私は初めてダミアの舞台を日比谷公会堂で聴くことができた。ちょうど私がラジオでデビューした年だった。産原英了先生からぜひ来るようにとお誘いを受けて二階席の正面に陣取り、初めて聴く本場のシャンソンに出合って感動した。
ダミアは、黒い袖なしのロングドレスに、真紅のスカーフを一本だけ使い、ピアノの前奏でとつぜん下手から現れた。万雷の柏手のなかで彼女はなんの愛想もなく、その赤いスカーフをなびかせながら上手のほうまで小走りに動き、舞台を大きく使って私たちの度肝をぬいた。バックはやはり黒のビロード風のカーテンだったから、いやが上にもダミアだけが引き立ち、彼女の手の動き、哀しげな表情が際立つのである。歌いながら中央に戻ったダミアは心をさらけ出すように歌いだす。シャンソン・レアリスト(現実派歌手)としての面目躍如である。言葉の意味がわからなくても、彼女の訴えている心情が伝わってくる。ダミアは、私が生まれて初めてじかに聴いたフランスのシャンソン歌手であっただけに、その強烈な印象は忘れることができない。
東京公演の翌日、私は銀座にあるシャンソン喫茶「銀巴里」で、ダミアが少人数のために歌ってくれる会に招待された。銀巴里はパリのシャンソン小屋風で数十人しか入れないから、産原先生のおかげで入場することができたようなものである。その夜、私は水谷八重子(先代)さんと、杉村春子さんの間の席でダミアを聴くことになった。私が音楽学校出身のシャンソン歌手の卵であることを知って、八重子さんはその隣に座っていた背のひょろりとした少女を紹介された。「娘の良重恵です。歌の勉強をしていますので、どうぞよろしく」と言われた。まだ十三歳くらいの水谷良重(現・八重子)さんはお行儀よく、ぴょこりとお辞儀をしてまた席についた。